目次
「ベラパミル」が不整脈用剤として処方されていた場合、特定薬剤管理指導加算1を算定できる?
(処方例)
Rp1)ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
3錠
分3 毎食後 30日分
答え 非表示
- Aできる
クイズの解説
「ベラパミル」の薬効分類は「217:血管拡張剤」で、「212:不整脈用剤」ではないため、「ハイリスク薬」には該当しません。しかし、『ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」』の適応には「不整脈」があります。そのため、「不整脈用剤」として処方されている場合には「特定薬剤管理指導加算1」の算定対象となります。

ただし、狭心症と不整脈どちらの場合も「1回40~80mgを1日3回」という用法は同じため、処方目的を確認するなどの対応は必要です。
こんな類似事例にも注意しよう!
以下の場合は「特定薬剤管理指導加算1」が算定できるかどうか考えてみましょう。
①『ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」』が狭心症に処方されている場合
②『ダイアモックス錠250mg』が抗てんかん剤として処方されている場合
③『バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」』が片頭痛発作の発症抑制で処方されている場合
ポイントは、処方目的が「特定薬剤管理指導加算1」の算定対象となる適応かどうかです。
①『ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」』が狭心症に処方されている場合:算定できない
『ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」』の薬効分類は「217:血管拡張剤」で、狭心症は「特定薬剤管理指導加算1」の対象となる適応ではないため、算定できません。
②『ダイアモックス錠250mg』が抗てんかん剤として処方されている場合:算定できる
『ダイアモックス錠250mg』の薬効分類は「213:利尿剤」で「ハイリスク薬」ではありませんが、「てんかん」の治療目的で処方されている場合には算定できます。
③『バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」』が片頭痛発作の発症抑制で処方されている場合:算定できない
『バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」』の薬効分類には「113 抗てんかん剤」と「117:精神神経用剤」が含まれるので、「ハイリスク薬」には該当しますが、片頭痛発作の発症抑制を目的で処方されているので算定できません。

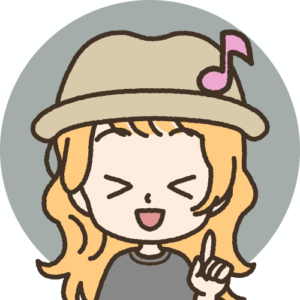
コメント