加齢による味覚の変化は、一般的には濃い味からあっさり味へと変わる、と思われています。ところがその反対に、中高年になって濃い味を好むようになる人も少なくありません。
なぜ、そんなことが起こるのでしょうか。
私たちが感じる味覚には、大きくわけると甘味、酸味、苦味、塩味の4種類があります。これらの味を、私たちは舌にある味蕾(みらい)というセンサーで感じています。
中高年になるにつれ、味蕾の細胞が減少したり、感度がにぶくなったりすると、少しずつ味がわかりにくくなります。個人差はありますが、4つの味覚のなかでもっとも感度の低下を自覚しやすいのは塩味です。
塩味の感度が低下すると、たとえばみそ汁などの味に物足りなさをおぼえるようになります。いつもと同じみそ汁なのに、「なんだか薄い」と感じたら要注意。あるいは料理の味が薄いと感じ、しょうゆやソースをたっぷりかけたりしていませんか。もし、そんなことがあれば、塩味をはじめ味覚の減退が起こっている可能性があります。
一般に味覚の感度が低下すると、無意識のうちに濃い味付けのものを好むようになります。それだけ塩分やカロリーの摂取量が増え、その結果、高血圧や肥満の一因ともなってしまうのです。

加齢によるさまざまな味覚変化
加齢にともなう味覚の変化は、味蕾によるものだけでなく、ほかにもさまざまあります。
唾液の減少もその一つ。唾液は食べ物を分解し、味を感じやすくする役割をもっています。それだけに唾液の分泌量が減ると、食べ物の味がわかりにくくなることがあります。
唾液の減少は自分ではわかりにくいのですが、なんとなく口のなかが粘つくようになったり、食べ物が飲み込みにくいと感じた場合には注意が必要です。
また、舌のうえに白いコケのようなもの(舌苔=ぜつたい)が多く付着した場合も、味を感じにくくなることがあります。舌苔は、味覚をにぶらせるだけでなく、口臭の原因ともなります。鏡で舌をみると自分でもわかるので、注意しましょう(胃の調子が悪いときも、舌苔が増えます)。

栄養のかたよりが原因で、味覚障害を起こすこともあります。その典型は、亜鉛不足です。
亜鉛は、味蕾の細胞がつくられるときに必要となる栄養素なので、不足すると味を感じにくくなります。若い人の場合は、ご飯(お米)をきちんと食べないために亜鉛不足を起こす例が多いのですが、中高年の場合には亜鉛の吸収力の低下が原因となりやすいのです。また、高齢者の場合には、食事の量が減ったり、同じようなものばかり食べることから、亜鉛不足を起こすこともあります。
脳梗塞の後遺症で味覚障害が起こることがあります。これは、味覚を脳に伝える神経経路(顔面神経、舌咽神経、脳幹、脳の味覚中枢など)が脳梗塞によって損傷されることが原因です。

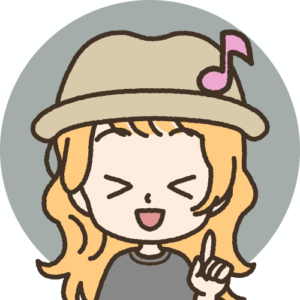
コメント