コルヒチンは、古くから痛風治療薬として、痛風発作の緩解や予防に使われている薬である。ロイコトリエン、インターロイキンなどに対する好中球の遊走性・反応性を低下させることにより、痛風の発作を抑制する。尿酸代謝にはほとんど影響しない。
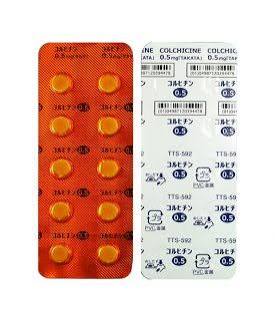
好中球は本来、体内に侵入する病原微生物を、活性酸素や加水分解酵素によって貪食・殺菌する。しかし、感染がないのに生体組織に好中球が浸潤・集積し、組織障害を来す疾患が幾つかある。ベーチェット病やスイート病、壊疽性膿皮症、持久性隆起性紅斑といった、好中球性の炎症性皮膚疾患もその1つである。これらの皮膚疾患は、従来の治療に抵抗性を示す難治例が多い。そのような場合に、好中球機能の抑制作用を期待して、コルヒチンが使用されることがある。

代表的な疾患であるベーチェット病は、好中球の異常活性化を特徴とし、多彩な症状を呈する。口腔粘膜のアフタ性潰瘍、皮膚症状、眼のぶどう膜炎、外陰部潰瘍を主症状とし、急性炎症性発作を繰り返す。皮膚症状としては、下腿に好発する結節性紅斑、皮下の血栓性静脈炎、顔面、頸部、背部などに見られる毛嚢炎様皮疹やざ瘡様皮疹などが挙げられる。