短時間作用型
| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランダキシン | トフィソパム | 1時間 | 1時間 | + | ± | ー |
| リーゼ | クロチアゼパム | 1時間 | 6時間 | ++ | + | ± |
| デパス | エチゾラム | 3時間 | 6時間 | +++ | +++ | ++ |
中時間作用型
| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイパックス | ロラゼパム | 1時間 | 1時間 | + | ± | ー |
| ソラナックス | アルプラゾラム | 1時間 | 6時間 | ++ | + | ± |
| レキソタン セニラン | ブロマゼパム | 3時間 | 6時間 | +++ | +++ | ++ |
| バランス | コントール | 3時間 | 10時間 | ++ | +++ | + |
長時間作用型
| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイラックス | ロフラゼプ酸エチル | 1時間 | 122時間 | ++ | + | ± |
| セパゾン | クロキサゾラム | 1時間 | 65時間 | +++ | + | + |
| セルシン ホリゾン | ジアゼパム | 1時間 | 54時間 | ++ | +++ | +++ |
| リボトリール | ランドセン | 2時間 | 27時間 | +++ | +++ | ++ |
パニック発作など、強い不安が急に起こる場合には、短時間や中時間作用型の薬を選び、不安感が長く続く場合には、中時間や長時間型の薬が勧められます。
なお、ベンゾジアゼピン系でない抗不安薬として、セロトニン受容体に作用するセディールという薬があります。
短時間作用型
| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セディール | タンドスピロンクエン酸塩 | 1時間 | 1時間 | + | ± | ー |

ベンゾジアゼピン系の抗不安薬よりも、効果の実感に時間がかかり、また抗不安効果も弱いという短所があります。
不安感が軽度である場合や、高齢の方など、ベンゾジアゼピン系抗不安薬による筋弛緩効果の副作用を避ける場合などに利用されます。
ベンゾジアゼピン系抗不安薬は、パニック症状の急性期の症状を抑えるには効果的ですが、耐性や退薬症状の問題がありますので、長期的な使用が必要な場合は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を使っていくことをお勧めします。
目次
妊娠中や出産後の服用に関して
妊娠時の服用による催奇形性については、統一した見解は得られていないものの、妊娠3ヶ月までのベンゾジアゼピン系抗不安薬の服用により、口唇口蓋裂のリスクを高める可能性があるようです。

授乳中での服用については、大人と同様の副作用、つまり、眠気や体の緊張の低下が赤ちゃんに起こる可能性があります。
また、薬を急にやめると、退薬症状として落ち着きのなさや不眠症状が起こる可能性があります。 服用が避けられない場合は、退薬症状を防ぐために、数週間かけて徐々に薬の服用量を減らしていくと良いでしょう。

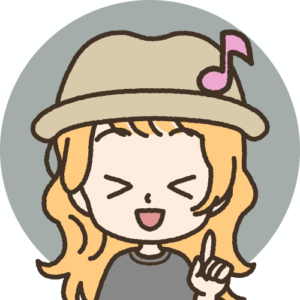
コメント